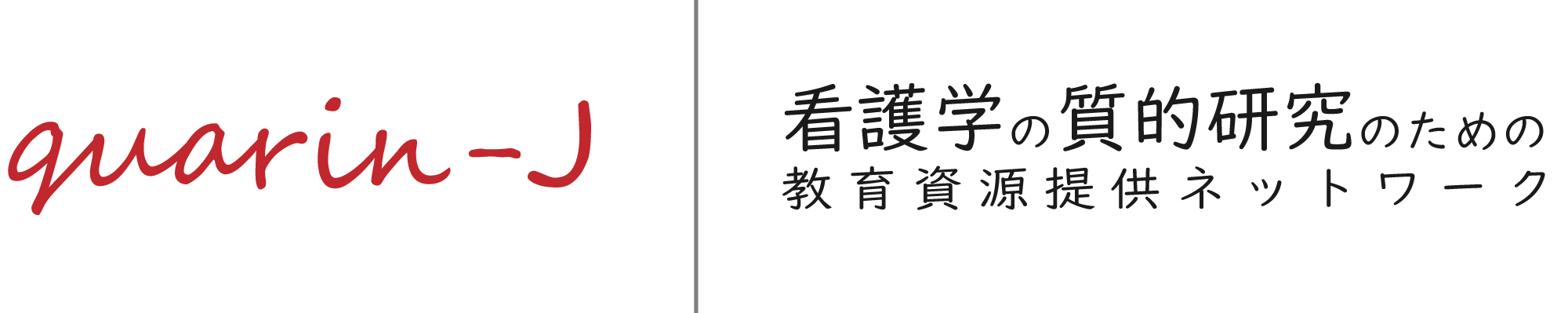木下康仁
このタイトルは正確には、データも古くならないとすべきなのだが、データは問いに順ずるのでとりあえずこのようにしておく。論文を完成させ研究が終われば、データも問いも用を果たしたことになるのだろうか。通常はそういう見方になろう。データは二次分析の場合もあるが実際にはそれほど多くはないし、次の研究では問いは新たに設定されるかもしれない。
対人援助領域での質的研究論文の査読をしていて感じるのは、解釈の薄さである。目的を設定し問いを立てデータを収集、分析し結果を出すという形にはなっていても、読んでいて「人間」が浮かんでこない。印象に残らない。部分的な内容からこちらが統合的に全体を理解しなくてはならず、読み手にそこまでの負担をかけるというのは分析が完了していないからである。「方法は問いに勝るのか」、「問いは方法に勝るのか」…研究では両者は一体とされるのだが、こうして分けて問うと自分の立場のあいまいさに気づきやすい。ここには数量的研究と質的研究の違いが反映してくる。
数量的データは数字であることによってすでに抽象化されたものである。どう分析するにせよ、そこから分析に入っていける。一方、質的データ、例えばインタビュー記録は、言わば生の内容である。複雑で多様な経験が個別、具体的にディテール豊かに表現されたもので、驚くほどの情報量の世界である。分析とは抽象化の作業であるから、質的研究ではこれを分析することになる。大変な力仕事で一筋縄ではいかない。簡単ではない。問いと方法を固めて挑まないと跳ね飛ばされるのだが、跳ね飛ばされていることに気づかずに作業をしているかもしれない。実際にはコード化、カテゴリー化が行われ抽象化された内容が言語化される。誰でもできることのようでもあるが、この言語的作業では健全な緊張感が求められる。一つの解釈に絞るには多角的な検討が必要で、どこまでいっても暫定的な結果でしかない。そういう理解で取り組むのが、緊張感の意味である。
こうした課題に対処するには、問いの設定が一般に思われているよりもはるかに重要で、生の内容である質的データは散弾銃のように広角度で分析者に向かってくる。多様であることによって分析者の関心が反応してしまうからである。問いの設定はそれを制御するためで、質的データの特性からオープンな問いを設定できる。オープンな問いとはなにがしかの普遍的な問いかけをもつもので、結果がでれば問いとして消えるわけではない。なぜなら、人間についての研究であり、人間は複雑な存在であるから。仮説検証や実態調査などと違い、深く検討されても明確な結論が得られない問い、問い続ける必要のあるもの、すなわち、一回の研究で用済みにできない問いとなる。実際にはある程度操作化した設定は必要になるとしても自分の中では問い続けるだけの問題意識をもつ。それが深い解釈を促すのであり、でないと分析は表面的になり、抽象化の結果が訴えてくる力をもてない。オープンな問いは古くならないし-結論は常に作業仮説-、終わりなき探求ができるような問いであれば、データにもまた出番がありうるからデータも古くはならない。